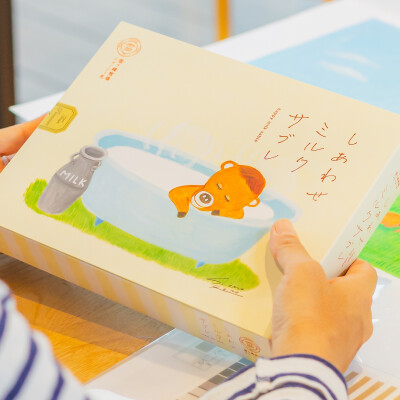2025.07.17
多様性を力に変える。「百様図」が示す大丸松坂屋百貨店の姿

取材・執筆:小泉ちはる 編集:末吉陽子 撮影:関口佳代
コロナ禍やデジタル販路拡大を契機に「大丸松坂屋らしさ」を見直す
――新ショッピングバッグのデザインは、今の大丸松坂屋の強みを再定義し、視覚化するVIの取り組みから生まれたと伺っています。VIプロジェクトはどのような経緯で発足したのでしょうか?
宗森耕二(以下、宗森):きっかけは主に2つあります。一つ目は、百貨店という存在が同質化していく中で、他社との差別化を図るために「大丸松坂屋らしさとは何か」を改めて見直す必要性に迫られたことです。
二つ目は、大丸と松坂屋という異なるアイデンティティを持つ百貨店の統合から10年以上経った今こそ、「私たちは何者なのか」を再定義するタイミングではないかと感じたこと。さらに言えば、会社と従業員が対等な立場で共創を目指していかなくてはならないこの時代、大丸松坂屋百貨店に対する共通認識を内部で共有する必要があると考えました。
これらの状況を踏まえ、2022年にブランディング戦略室を設立し、「大丸松坂屋らしさ」を再定義しようという取り組みを始めたのです。
――「大丸松坂屋らしさ」を再定義するにあたり、どのようなアプローチから開始されたのでしょう?
宗森:本社と全国の店舗に「どういうところが強みだと思うか」「どのような存在でありたいか」といったヒアリングを行いました。大丸松坂屋は全国に店舗を展開しており、各々の地域のお客様から厚いご支持をいただいております。そこで、まずは現場にこそ答えを求めるべきだと考え、店舗で働く従業員の声を一つ一つ吸い上げました。
それを通して判明したのは、店舗によって強みも個性もお客様からの認識も全く異なるということ。一緒にヒアリングした外部のクリエイターは「まるで違う会社に来たみたいだ」と驚いていたほどです。
一般的に、大手の系列店は本部が各店舗へ一括して指示を行うセントラルバイイング方式を採用しているところも多いため、全国どこでも均一的な売り場・サービスになる傾向があります。しかし、大丸松坂屋では各地域のお客様のニーズやマーケットにフィットしようと独自の工夫を重ねた結果、それぞれの店舗に個性が備わりました。
たとえば、お客様一人ひとりに寄り添った丁寧な接客を重視する店舗もあれば、スピーディーな対応に尽力するターミナル店もある。まさに多様です。こうした状態を俯瞰して見ると、全国主要7都市15店舗の「多様性」こそ、大丸松坂屋の強みなのではないかと感じました。

大丸松坂屋百貨店代表取締役社長の宗森耕二氏
――多様性による違いをなくして一つにまとめるのではなく、あえて活かす方向に舵を切ったというわけですね。その背景には、どのような考えがあったのでしょうか?
宗森:大丸松坂屋の多様性は、JFRグループ全体が目指している「価値共創リテーラー戦略」と、方向性や価値観でつながっています。
この戦略は「感動共創」「地域共栄」「環境共生」の3つを柱としています。「感動共創」は、お客様や従業員とともに感動を生み、それを分かち合うこと。「地域共栄」は、地域の魅力を高め、なくてはならない存在になること。「環境共生」は、誰もが環境に配慮した社会づくりに貢献できる文化を育てることを目指しています。
大丸松坂屋が大切にしている多様性は、「感動共創」「地域共栄」「環境共生」というJFRグループの3つの柱すべてに貢献できる力があります。
価値観が大きく変化する今の時代において、大丸松坂屋は、人や地域とのつながりを深めながら、過去の価値観とこれからの価値観をつなぐ「橋渡し」のような存在になれる。そして、社会から求められるリテーラーとして、これからの暮らしに新しい幸せを届けていけると確信しています。
そのためにまず必要なのは、「大丸松坂屋らしさ」を従業員一人ひとりに心から共感してもらうことです。どうすればそのメッセージを直感的に伝えられるのか、ブランディング戦略室の寺井室長とともにその答えを模索してきました。
「4つのまなざし」をもとに、多様性を視覚的に落とし込んだ「百様図」が誕生
――従業員の皆さんのマインドセットを変えるため、最初にどのようなステップからはじめられたのでしょうか。
寺井孝夫(以下、寺井):各店舗を巡り、「私たちはバラバラでいい」というメッセージを根気よく伝えました。その際、課題となったのは店舗のアイデンティティと会社全体のアイデンティティとのバランスです。全国15店舗の持つ個性が大丸松坂屋の強みであると認識したものの、それを視覚化するにあたり壁にぶつかりました。というのも、先ほど宗森が申し上げた通り、当社は実店舗を中心に考えられてきた会社であり、店舗のアイデンティティが頂点にあります。
しかし、私たちがフィルターをかけていこうとしているのは、店舗のアイデンティティが頂点にある中で、その屋号の下にある 会社全体の持つ強みです。その調整にあたり、全店舗の、2つのアイデンティティを内包するものとして、私たちはまず「4つのまなざし」を設定しました。

VIの構想に携わったブランディング戦略室室長の寺井孝夫氏
――「4つのまなざし」とは、どのようなものでしょう。
寺井:一つ目は、絶え間ない変化と気づきの瞬間を表す「移ろいへのまなざし」。二つ目は、伝統とともに新しいものを大切にし、次世代へつないでいく「歴史へのまなざし」。三つ目は、その地域にしかないものの価値を見極め、再解釈して提供していく「土着へのまなざし」。四つ目は、無機質な存在ではなく、人の手触り感やヒューマニティを重視する「気持ちへのまなざし」です。
この「4つのまなざし」をもとに、私たちの目指す大丸松坂屋のあり方を視覚的に落とし込んだ「百様図」のデザインを制作しました。
――「百様図」の制作にあたり、こだわられたポイントはありますか?
寺井:大丸松坂屋には、さまざまな土地や人とつながる店舗があります。そうした背景を踏まえ、「紙」と「丸・四角」というシンプルな素材と図形を重ねてずらすことで、まったく異なる表情や変化が生まれるようにデザインし、多様性や文化の重なりを表現しています。
一見するとCGのようですが、じつは4種の色紙に丸や四角の穴を開けて重ね、写真に撮ることで仕上げています。そのため、紙を少し動かすだけで、まるで表情が変わるような印象を与えるように工夫しました。
また、色づかいにもこだわっています。大丸のCIカラーであるピーコックグリーンと、松坂屋のCIカラーであるロイヤルブルーをメインカラーとして採用し、それぞれの歴史や大切にしてきた想いを受け継ぐかたちにしています。

「『百様図』は大丸松坂屋のあるべき姿を表現したもの。私も『百様図』の紙を社用のスマホケースに挟み、肌身離さず持っています」と語る寺井氏
――「百様図」を用い、どのような取り組みをしておられますか?
寺井:「百様図」を直接店舗に持参して説明したり、「百様図」を表現した紙を36種類用意して従業員に選んでもらうワークショップを実施したりしました。
また、従業員にとって触れる機会の多いショッピングバッグのデザインを、2025年7月から「百様図」に変更いたします。ショッピングバッグの変更は、実に数十年ぶりのこと。これは、従業員に「われわれらしさ」を再認識し、行動様式を変えてもらうための仕掛けなのです。
――従業員方の反応はいかがでしたでしょうか?
寺井:「誇りを取り戻せそうな気がする」「子どもに伝えたい」というコメントを受け取ったときには、思わず胸が熱くなりました。
とはいえ、こうしたブランディング活動に終わりはありません。様々なセクションで働く従業員のマインドが変容し、実務に反映されるまで、長期的合理性を大切にしつつプロデュースし続けていくつもりです。
「先義後利」「 諸悪莫作 衆善奉行」に立ち返り、お客様とともに価値を共創する
――「百様図」を起点に、これから社内外にどのようなメッセージを発信していきたいですか?
宗森:お客様からは「大丸・松坂屋で買いたい」と思われる、従業員からは「こんなに良い商品を売るなら是非自分の店舗で」と思われる、お取引先様からは「商品を大丸松坂屋の店舗で扱ってほしい」と思われる、この循環ができるのが理想です。
そのためには、大丸松坂屋の社是である「先義後利(義を優先し、利益を後にする)」「 諸悪莫作(悪いことをしない) 衆善奉行(多くの善を実行する)」に立ち返りつつ、お客様や社会のニーズに応え、新たな価値を提供していくことがわれわれの役割だと考えています。

「ひと言で従業員といっても、バイヤーや接客、人事など置かれた立場はさまざまです。一人ひとりが向き合っている人たちに対して、真摯に価値提供を行ってほしい」と語る宗森氏
従来は、あくまでもお客様は「神様」であり、共創のパートナーとしての視点で見ていませんでした。しかし、価値共創リテーラーを目指し、これからはお客様も含めた全てのステークホルダーとともに価値を創造していくというビジョンを描いています。だからこそ、お客様・取引先様・当社の三者で新しい幸せや百様な豊かさをプロデュースしていく、そしてそこに共感していただくことが重要です。本質的なファンづくりと言い換えてもよいでしょう。
いままでは当社のファンになるきっかけとして、カードのポイントアップや優待などのインセンティブの価値が機能してきました。しかしこれからは、本質的な当社のファンづくりのために、新しい価値を生み出し、機能させていかなければならないと考えています。
時代に合わせて新たな価値を見出したり、お客様へ提供したりするのが私たち小売業の仕事であり、要です。それを一途に実行し続けることこそ、必要なのではないかと感じています。
――「大丸松坂屋らしさ」を追求し、新しい価値を提供した結果、社会的にどのような影響が生まれるとお考えでしょうか?
宗森:社会的な影響については、すぐに答えが出るものではありません。しかし、今の積み重ねが私たちの未来を作るのは間違いない。300~400年続いてきた歴史ある百貨店として、次の世代にしっかりバトンをつないでいけるよう、愚直に役割を果たしていきたいです。
そのためにも、店頭で従業員やお客様、取引先様に「大丸松坂屋らしさ」を感じていただける成功事例を小さくてもよいから作り続けていく。そして、価値観を共有し、より深い理解につなげることで、大丸松坂屋らしい小売業や百貨店のあり方を追求していきたいと考えております。